「働く人のこころの健康相談室 2010年4月~2010年3月」の利用状況
2011年5月30日
茨城産業保健推進センターでは、2007年12月から、毎月2日(毎月第2・第4月曜日、ただし祝日・年末年始等を除く)、「働く人のこころの健康相談室」を設け、勤労者のメンタルヘルスに関する相談を受け付けてまいりました。
このたび、2010年4月~2010年3月までの利用状況を、下記のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。
平成22年度「働く人のこころの健康相談室」の利用状況
- 相談期間
2010年 4月1日 ~ 2010年 3月30日
(3月は東日本大震災により1日のみ実施) - 相談日数 38日
- 相談者数 延71名 228件(実人数44名) ※1
- 相談数・件数の推移
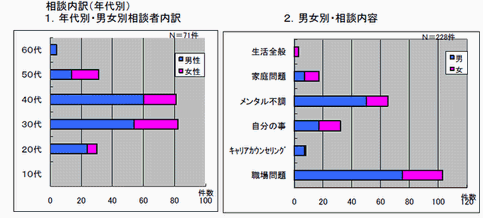
- 相談内容
- 相談結果 ※2
- 年代別:40代・30代、50代と20代の順に多く、40代・30代で66%を占めていた。
上司や親からのメンタル不調者対応方法、休職から復職への対処法の相談が3割を占めた。 - 男女別:22年度は、前年度までに比べ男女比が逆転、
男:女=7:3(←男:女=4:6)で、遠距離からの電話相談が増えた。 - 相談内容:
- 男性・女性共に、①メンタル疾患 ②職場の問題 ③家庭の事 ④自分の事・生活全般の順だった。
- 職場の問題では、①人間関係 ②仕事の負担 ③労働条件についての順だった。
- メンタル疾患は、①不調者の相談 ②本人及び上司の復職中・復職前後の対処方法の相談を含んでいた。
- 上司や親が現状打開の注意点・受診への繋ぎ方など対応法に困った相談件数が増加した。
- 女性は上記と、家庭問題や生活全般の問題も多く、1人で複数の問題を抱えている人が多かった。
- メンタル問題は、職場の問題+個人の性格が関与する傾向が増加し、相談対応が難しくなっている。
- 年代別:40代・30代、50代と20代の順に多く、40代・30代で66%を占めていた。
- 相談結果 ※2
- 相談の対応
- 継続せざるを得ない複数例の面接は、傾聴により現状・気持ち、問題の明確化・整理の支援を心がけた。
- 話しを聴きながら、現状が少しでも楽になれる方法を一緒に考え、出来る事を探していった。
- 重症事例が多くなり、変動する気持ちを受容しつつ自己の状況把握と対処ができるように配慮した。
- 良い状態へ改善するために、生活リズム(睡眠・生活習慣)を良くし体調改善ができるよう配慮した。
- 深刻事例・不安定者には、治療を受けている事を条件に連携を取りつつ複数回の面接を行った。
- 事例(相談者の事情)によっては、休業から復職までを支援、復職ができた。
- メンタルヘルス研修の実施と併せて、面接対応し職場の対応について支援をした事例も増えた。
- 相談者の反応
- 話を聴く事で、下記の感想が聞かれた。
- 「誰にも言えなかった事を話せて良かった」
- 「今の状況・気持ち、問題点が理解できた」
- 「問題点が明確になった」 「整理ができ少しスッキリできた」
- 企業の困難事例は、研修実施で対処法の知識共有化を図り「今の状況への対応が明確になった」
- 事例によっては、休業から復職トライ・転職トライ(適職探し)への支援をし、準備行動に移せた。
- 話を聴く事で、下記の感想が聞かれた。
- カウンセラーとしての感想
- メンタル疾患の休業中の過ごし方やリハビリの仕方は、本人任せでフォロー・サポート者がいない。休業中の適切な支援は、早期職場復帰への手助けになる。支援者・理解者不在の事例は、職場復帰が遅れやすいため必要に応じて相談回数を重ね支援を行い、復職につないだ。
- 復職後の感情・行動の変動は避けられない。自殺念慮者の支援に関わる事も多く、職場の対応も大変さが伺えた。メンタルヘルス研修の実施により、職場で共通知識・認識を持ち早期発見・早期対処できることが望ましい。
- 研修による知識の共有化で、早期発見・上手に対処できる支援と共に、休業中の相談対応の必要性も感じた。
メンタル対応は、個々に対処法がちがい、個別の対応が求められる。気軽に相談していただき、個々に合う適切な対処法の支援で早く職場復帰を出来るよう支援して行きたい。
苦しみ、悩みを軽減し、早く苦しみから脱出できる、その人らしく有意義な人生を送れるように支援する役割は大きいと感じた。
◆2008年~2010年の相談の推移
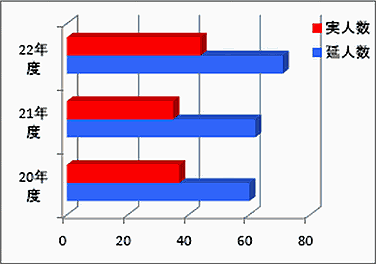
相談人数の推移
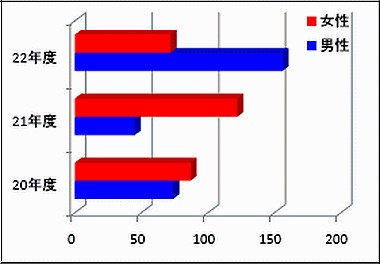
男女別・延べ相談件数の推移
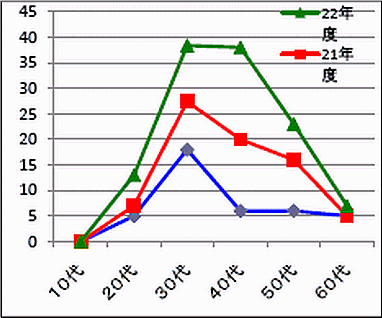
年代別男女別相談延べ人数
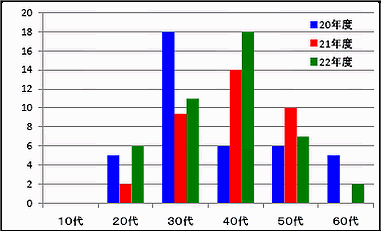
年代別男女別相談実人数
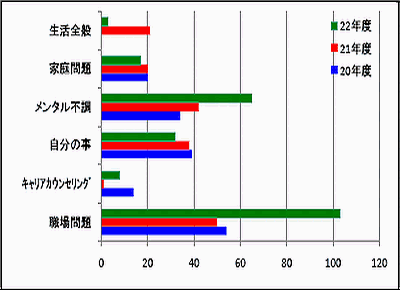
延べ相談内訳の推移
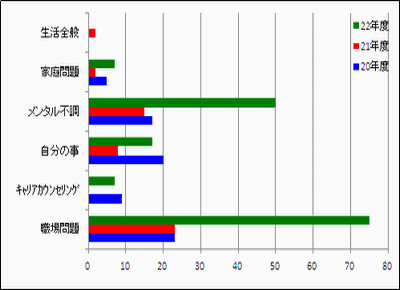
男性 相談内訳の推移(延べ)
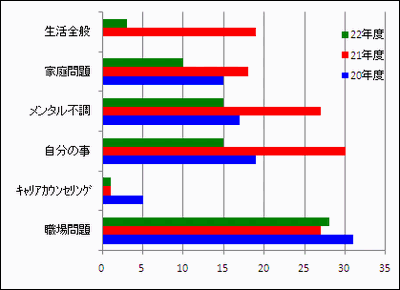
女性 相談内訳の推移(延べ)
※1 相談時間は、概ね1時間程度以内としている。
※2 相談方法は面談又は電話。費用は無料(通話代は相談者負担)。
